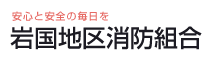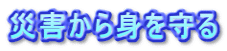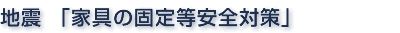地震の揺れで、家の中の家具が倒れたり、ガラスが割れたりして、多くの人がけがをしています。「寝室には家具を置かない。」のが一番ですが、無理な場合でも、倒れづらい低い家具を置いたり、家具が倒れても安全なスペースをつくるなどの工夫もしてみましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | まずわが身の安全を守れ | 2 | すばやい消火、火の始末 | |
| 何よりも大切なのは命。 地震がおきたら、まず第一に身の安全を確保する。 |
火を消す3度のチャンス
|
|||
| 3 | あわてた行動けがのもと | 4 | 窓や戸を開け、出口を確保 | |
| 屋内で転倒・落下した家具類やガラスの破片などに注意する。 | 小さな揺れのとき又は揺れがおさまった時に、避難できるよう 出口を確保する。 | |||
| 5 | 落下物、あわてて外に飛び出さない | 6 | ブロック塀などに近づかない | |
| 瓦、窓ガラス、看板などが落ちてくるので注意する。 | 屋外で揺れを感じたら、ブロック塀など建物に近寄らない。 | |||
| 7 | 正しい情報、確かな行動 | 8 | 確かめよう、わが家の安全、隣の安否 | |
| ラジオやテレビ、消防署、行政等から正しい情報を得る。人の噂話に惑わされないようにする。 | わが家の安全を確認後、近隣特に災害時要援護者の安否確認。 日頃から近隣のお年寄り等、災害時に介添が要る人の把握もしておいて下さい。 |
|||
| 9 | 協力し合って救出・救護 | 10 | 避難の前に安全確認、電気・ガス | |
| 倒壊家屋や転倒家具などの下敷き担った人を元気で避難された方々で協力し、救出・救護する。 救出の速さが生死の分かれ目と なります。 | 避難の前に、可能であればブレーカーを切り、ガスの元栓を締めて避難する。無理をしないように注意が必要。 | |||
|
お年寄り・乳幼児・障害者・外国人災害時に大きなハンディを持った人たちが多くいます、こうした要援護者の被害が増加しています。 |
||
| 災害弱者の身になって防災環境の点検を | 避難する時はしっかり誘導する | |
| 避難経路は車椅子で通れるようになっているか、放置自転車などの障害物はないか、耳や目の不自由な人への警報や避難勧告の伝達方法はあるかなど、災害弱者に対応した環境づくりを。 | 災害時に避難するときは、お年寄りや乳幼児などをしっかり保護する。手をつなぐ、背負うなど。また、障害者などに対して地域で具体的な救援体制を決めておく。 | |
| 困ったときこそ弱者に温かい気持ちで | 復旧活動にも積極的に参加してもらう | |
| 災害時の混乱や被害が大きいほど、誰もが殺伐とした気持ちになりがち。しかし、そんな非常時にこそ、困っている人や災害弱者に対して温かい思いやりと真心を。 | 被災後の復旧活動の際に、積極的に参加してもらいましょう。何もしないでいることがかえってストレスや体調を崩す原因になります。活動の目標を決めて毎日適度に体を動かせるように配慮しましょう。 | |
| 岩国地区消防組合消防本部 | 〒740−0037 岩国市愛宕町一丁目4−1 TEL : (0827)-31-0119 FAX : (0827)-32-1119 MAIL : ifd119@joy.ocn.ne.jp |
|